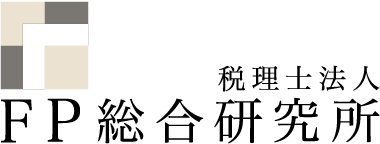【No777】裁判例から学ぶ相続対策における意思能力の重要性
普通方式の遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があり、それぞれメリット・デメリットが挙げられますが、「法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度」の創設により、これまで自筆証書遺言のデメリットとされてきた、遺言書の紛失や隠匿等の防止が図られ、遺言書の存在の把握が容易になる効果も期待されるようになりました。他方で、「人生100年時代」と言われるように長寿化が進んだことにより、自筆証書遺言(秘密証書遺言も)については、遺言の解釈以上に、「遺言能力(遺言をするために必要な意思能力)」が問題視されるようになってきてもいます。
今回ご紹介する判決(東京地裁令和2年10月8日判決)は、直接、自筆証書遺言とは関係しませんが、後見開始の審判を受ける前に行った「死因贈与契約」の有効性が争われており、実務的に参考になる点が多いのではないかと思われます。この事件では、贈与者の意思能力の有無は判断されていませんが、死因贈与契約の締結時に、弁護士2名が立会うだけでなく、贈与者が契約内容を適当に理解していることを証する書面(確認書)まで作成していました。親族内の紛争が当初からあった事件ですが、高齢者による遺言作成には、第三者による本人の遺言能力の確認が重要となる点が理解頂けるのではないかと思います。
1.事件の概要
この事件は、被相続人Aの二女である原告Xが、Aとその長男である被告Yが締結した「死因贈与契約」は、Aの錯誤により無効であると主張して、その確認を求めた事案です。事実関係は以下のとおりです。
Aと夫Bとの間には、X(二女)とY(長男)の2人の子がいました。Bは不動産賃貸業を営んでいましたが、Bが高齢になってからは、Yが物件管理を行うようになり、その後の建物建築資金などはYが連帯債務者や連帯保証人として、Bとともに債務を負担していました。平成27年11月5日、Bが死亡した後、Aは介護を要する状態となり、デイサービスやショートステイの利用、入通院等の手配など、Aの身上監護はYが行うようになりました。これに対しXは、平成28年9月9日、弁護士2名を連れてAを訪問した以降、Aと面会することは一度もありませんでした(XとY、AはBの遺産分割でもめており、その後の平成29年2月頃、AとYは、Xに対し、遺産分割調停を申し立てています)。平成28年10月13日、Xは、家庭裁判所に、Aについての後見開始の審判の申立てをしました。そこで、AとYは、平成28年11月30日、弁護士2名の同席の下、Aの所有する財産全てを死因贈与により、Yへ移転する旨の契約を締結するとともに、Aがその内容を理解していることを確認する書面も作成しました。その際、Aは、YがBの債務を相続し、弁済を行っていること。そして「現在、Aの身上監護に常に心を砕いているのはYであり、Aは、自らが日々平穏に暮らせているのは、Yのおかげであると感謝している。そこで、Aは今後も命ある限り、Yが支援してくれることを望む。」と付言しました。平成29年2月8日、Aは、医師により、晩発性アルツハイマー病の認知症に罹患していると診断され、平成29年4月11日、後見開始の審判が行われました。Aの後見人が、平成29年9月28日に家庭裁判所に提出した後見等事務報告書には、YがAの財産を事実上管理していたこと、Aは財産管理や身上監護についてYに任せている旨の発言をして満足している様子であったことなどが記載されていました。そして、平成31年4月26日、Aは死亡したため、XがYに対し、「死因贈与契約」の無効について、訴えを提起しました。
2.裁判所の判断
裁判所は、AとYとの死因贈与契約は、Aが、Yが借入金債務の連帯債務や連帯保証を負い、それらの弁済を主導していたことから、Aの介護に関与していたYがAの死亡後もそれらの弁済に窮することのないように、従前それらの弁済の原資とされてきたAの財産をYに引き継がせようと考え、締結したものとみる余地があるとした上で、Aが錯誤に陥って本件契約を締結したとはいえず、Xの主張は採用できないと判断しました。
民法は、契約締結には、その人に契約内容や効果を理解することができる能力(意思能力)が必要としています(民法3条の2)。後見の審判が、本人が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合(民法7条)に行われることを考えると、死因贈与契約締結時、満91歳であったAの意思能力があったか否かは重要な論点となりますが、裁判所はAの意思能力の有無について、何ら触れることなく、Xの主張を退けました。裁判所の判断に、死因贈与契約時に弁護士2名が立会い、確認書を作成していたことが影響したのかもしれません。上述したように、死後の紛争を避けるための遺言が紛争を招かないよう、高齢者による遺言作成には、第三者による本人の遺言能力の確認が重要になるものと思われます。
(文責:税理士法人FP総合研究所)