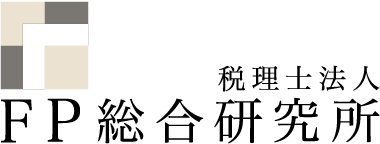【No844】最高裁判決 マンションの相続財産評価で納税者敗訴
一審、二審と争われてきました、相続税申告におけるマンションの評価額(財産評価基本通達6項)を国が更正処分した事案について、4月19日に最高裁の判決が確定し、納税者の上告を棄却し納税者が敗訴となりました。この事案の内容を解説します。なお、事案の概要は令和3年6月11日「№776賃貸マンションの相続税評価に関する最新の判例について」に記載しています。
1.財産評価の前提
相続税の申告における財産評価については、相続税法22条において「相続等により取得した財産の価額を当該財産の取得の時における時価」とされています。しかし、時価をどうやって求めるかを法律には規定していません。
そこで、国税庁が財産評価の一般的なマニュアルとして「財産評価基本通達(以下「評価通達」とします。)」を作成し、多種多様な財産の時価の評価方法について一定の基準を設け、納税者の不公平が起きないように、また申告実務においても簡便に行えるようにしています。
なお、この評価通達6項には、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」とされており、つまりは通達の定められた方法により評価したが、それが「著しく不適当と認められる」場合には、課税庁から指示を受けた評価とすることになります。しかし、この評価通達6項がどういった場合に適用されるかの具体的な記載はありません。
2.判決の内容
この事案は、相続人が相続した不動産を通達の定める方法で評価し申告していましたが、札幌南税務署長から評価通達6項に基づき鑑定による評価額で評価すべきとして更正処分等を受けています。ここでは、判決で主に論点となった点を解説します。
(1)相続税法22条と評価通達6項
最高裁は、評価通達は行政機関内の職務権限行使を指揮するもので法的効力はなく、相続税法22条における客観的交換価値としての時価を上回らない限り同条の法律に違反するものではないため、課税庁が評価通達6項を適用し評価した鑑定評価額(以下「鑑定評価額」とします。)が、納税者が評価通達6項の適用がないものとして評価した通達評価額(以下「通達評価額」とします。)を上回るか否かによって左右されないと判断されました。
よって、鑑定評価額は不動産の時価として認められ、通達評価額を上回るからといって、相続税法22条の違反とはならないと考えられたことになります。
(2)租税法上の一般原則である「平等原則」
納税者は、特定の者だけ通達評価額ではなく鑑定評価額とすることは平等ではないと主張しています。
これに対し最高裁も、たとえ客観的交換価値である時価を上回らないとしても、特定の者だけ通達評価額を上回る価額で評価することは合理的な理由がない限り平等原則に違反し違法としています。しかし、評価通達に定める方法により画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、平等原則に違反しないとしています。
鑑定評価額と通達評価額に大きな乖離があること自体は評価を見直す合理的な理由ではないとしたうえで、当該物件購入が税負担を大幅に減少させることを意図して相続開始の直前で購入・借入しており、結果として同様の対策を実施していない他の納税者との間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な税負担の公平に反するとし、納税者の訴えを棄却しました。
3.判決を踏まえての問題点等
今回は、評価額、納税額への影響がどれだけ生じれば評価通達6項を適用するといった形式的な判断基準を明確にした判決ではなく、節税対策とはいえ富裕層が約6億円もの財産を対策により圧縮し税額を0円としたことが、社会通念上(国民感情的に)許しがたい、つまり「やりすぎ」と判断されたといえるでしょう。国の立場で考えれば、明確な判断基準を設けることは、その基準を敢えて外すための対策が行われることとなるため、どこまでは問題ないという基準を明示することは困難であったのではないかと推測されます。
評価通達6項の適用にお墨付きが与えられたわけですから、そのリスクを考え不動産を購入、建築しているケースについて実際にどのように不動産を評価するのか悩ましいところです。これについては、税理士の立場であれば、納税者への説明責任を果たし、どのような評価方法とするかを相談しながら進めていくしかないと考えます。
(文責:税理士法人FP総合研究所)